アニメ『ある魔女が死ぬまで』は、一見すると明るい魔法ファンタジーだが、その物語の核には「死」や「正義」といった普遍的なテーマ、そして現実社会の問題が据えられている。
あらすじ
見習い魔女のメグ・ラズベリーは、17歳の誕生日に師である「永年の魔女」ファウストから、余命1年の呪いを受けていることを告げられる。呪いを免れる方法は、人々の嬉し涙を千粒集めて「命の種」を生み出すこと。メグは涙を集めるために多くの人と関わりながら、出会いと別れを繰り返し、魔女として成長していく。
第1話 余命一年の魔女
第1話のテーマは「死の受容」であると考える。
あらすじに「余命1年の呪い」と書いてあるので重たい話なのかと思いきや、冒頭からポップでカジュアルな雰囲気で物語が進む。とにかく主人公メグの性格が良い。明るくポジティブ。実質魔法使いプリキュア。
亡き母を思う少女に「桜」を見せるメグの魔法は、失われた命を蘇らせるのではなく、残された者が死を受け入れるための慰めとして描かれる。魔法は「死者のためではなく、生きる者の幸せのため」にあることが示される。
第2話 見習い魔女とラピスの人々
ここでのテーマは「良い死とは何か」であると考える。
修繕できなかった時計を精霊の開放によって「供養」する場面や、死期を悟ったフレアおばさんとの交流を通じて、御神木の下での「安らかな最期」が描かれる。そして第1話と同じく、死に関わる行為は死者のためではなく、あくまで生きる者のためにあることが強調される。
第3話 東より、英知の来訪
祈さん登場回。
ここでのテーマは「気候変動と環境汚染」であると考える。
「気候、環境に手が入りすぎておかしくなっている」
という台詞はもちろんのこと、加えて
「お偉いさんは利益を貪ったあとに、魔法で解決できると思っている」
という台詞は、「魔法」をこちらの世界における「科学」として読み替えることで、現代社会への高い批評性を感じられる。
また、
「感情っていう要素は現代魔法ではほとんど使われていないのよ」
という台詞においても、「魔法」を「科学」に読み替えることで、科学万能主義に対する問いかけと読むことができ、「感情」という要素の重要性が示唆されている。
第4話 祝福は開門と共に
第5話 祭典の夜空に花は咲く
2話まとめてソフィーとの友情回であり、その他で異種族間恋愛が描かれる。
天才ゆえに迫害され、魔法を消したいと願うソフィーは、「魔法=喪失」の記憶を重ねている。そして「魔法の門」はソフィーの閉じられた心のメタファーにもなっており、メグと一緒の時間を過ごすことでその氷は徐々に溶けていく。ここでは新たに「魔法=つながり」というモチーフが提示される。
第6話 魔法のない夕暮れの空は
ここでのテーマは「偽善」であると考える。
涙集めに慣れ、形式的な行動になってしまうメグは、自分の偽善を意識して落ち込む。
しかし、「やらない善よりやる偽善」言葉があるように、行為そのもので他者を救っていた事実は揺るがないと私は考える。
この物語上では「一人ひとりに真摯に向き合う」ことの重要性が説かれている。しかし、むしろ「偽善や不完全な状態であっても人を救うことができる」という事実は、ある意味で希望として捉えられるのではないかと考える。
第7話 言の葉と災厄と式典と
魔法式典および新登場キャラクターの紹介回。
「人工の星の核」を用いた魔法システムは原子力発電や核融合を思わせる。「魔力の流れを人の手でコントロール」しようとする姿からも、現代社会のエネルギー問題に関しての語りと読むことができる。
第8話 悪魔に魅入られた家族
「悪魔の刻印」や「悪魔崇拝」について。テーマを表面的に読めば陰謀論だが、構造としては闇金や身売りのほうが近いといったところか。
「魔女は万能じゃない。両手を広げた範囲に収まる人だけを守るんだ」
お師匠様、親指が……!
自分の信念に従って正義を定義・自分で決めたことは貫き通す
「悪魔崇拝」というモチーフについて、ここでの構造としては闇金や身売りが近く、さらに抽象的には「搾取」がテーマとして浮かぶ。
また、
「魔女は万能じゃない。両手を広げた範囲に収まる人だけを守るんだ」
という台詞は、「万能主義の否定」と「救済の限界」を提示していると考える。
第9話 古き大樹は眠る
街の御神木が魔力汚染で変質してしまったため、仕方なく燃やすという話。
そこにメグにだけ視える御神木の精霊が現れ、精霊の希望でメグは街を案内する。
すっかり仲良くなったメグは御神木の精霊から名前をつけてほしいと言われ、「セレナ」と名付ける。
御神木を燃やす当日、変質した魔力が強まり、用意していた結界は破られ、「セレナ」は魔力汚染によって異形化してしまう。
もうどうすることもできないと思われた中、メグは御神木を「オーク」から「桜」へ転生させることで解決する。
後日、魔法史に残る大魔法を成し遂げたメグは、転生魔法によって生まれ変わった新種の樹に新しい名前をつけなければならないということから、その桜の樹を「ラピス・セレナ」と名付ける。
第1話の「桜」、第2話の「御神木」、そして第9話の「セレナ」をすべて回収する美しい構成であり、自然と人間との関わりを象徴的に描き出している。最も綺麗で素晴らしい回。
第10話 潮騒と共に祝福の鐘は鳴る(前編)
第11話 潮騒と共に祝福の鐘は鳴る(後編)
水の都アクアマリンの街を舞台に、「生命の扱い方」がテーマであると考える。
転生魔法による魔力汚染者の治療では、「終末医療の在り方」として、避けようのない死の前では、一縷の望みにかけて治療をするべきだという主張が展開される。
また、街に迫りくる津波からの避難では、誰をどの避難所へ誘導するかという問いから、助ける命と助けない命を選ぶ「命の選別」という倫理的ジレンマを迫られる。
物語としては、大魔女テティスの作った魔法の鐘をメグが鳴らすことによって街が守られる。
ご都合主義的とも捉えられる結末だが、ジレンマを乗り越えたアウフヘーベンとしての結末と捉えることもでき、同時に「救済の物語」としては必然でもあった。
第12話 私の愛した人たち
魔女エルドラ回。エルドラの過去と軍事国家オルロフの存在を通じて、魔法の発展がもたらす社会的・経済的な対立が描かれる。軍需産業と魔法の関係は、現代のAIやロボットによる産業構造の変化にも重なる。
また、メグの「過去も未来もそれが私に必要かどうかは私が決める。私は自由」という言葉は、自分の人生を自分の意思で選び取る姿勢を示しており、これまでの問いかけの物語を締めくくるにふさわしいといえる。
まとめ ファンタジー作品で現実社会の問題を語ることの意味
アニメ『ある魔女が死ぬまで』は、ファンタジーでありながら「死」「正義」「終末医療」「環境問題」「社会的対立」といった数多の現実社会の問題を照射する作品であった。
ここで重要なのは、それがファンタジー作品だからこそ効果的だったという点だ。現実の出来事をそのまま描けば視界が曇る。そこをあえてファンタジー世界で語ることで、むしろ澄み渡った見通しを私たちに与えてくれている。
ファンタジーという虚構を媒介として、いつのまにか私自身が、現実社会の本質を浮かび上がらせる魔法をかけられていた。
【リンク】
単行本『ある魔女が死ぬまで -終わりの言葉と始まりの涙- 』(電撃の新文芸)
Kindle版『ある魔女が死ぬまで -終わりの言葉と始まりの涙- 』(電撃の新文芸)
コミック(紙)『ある魔女が死ぬまで 1 終わりの言葉と始まりの涙 』(電撃コミックスNEXT)
Kindle版『ある魔女が死ぬまで 1 終わりの言葉と始まりの涙 』(電撃コミックスNEXT)
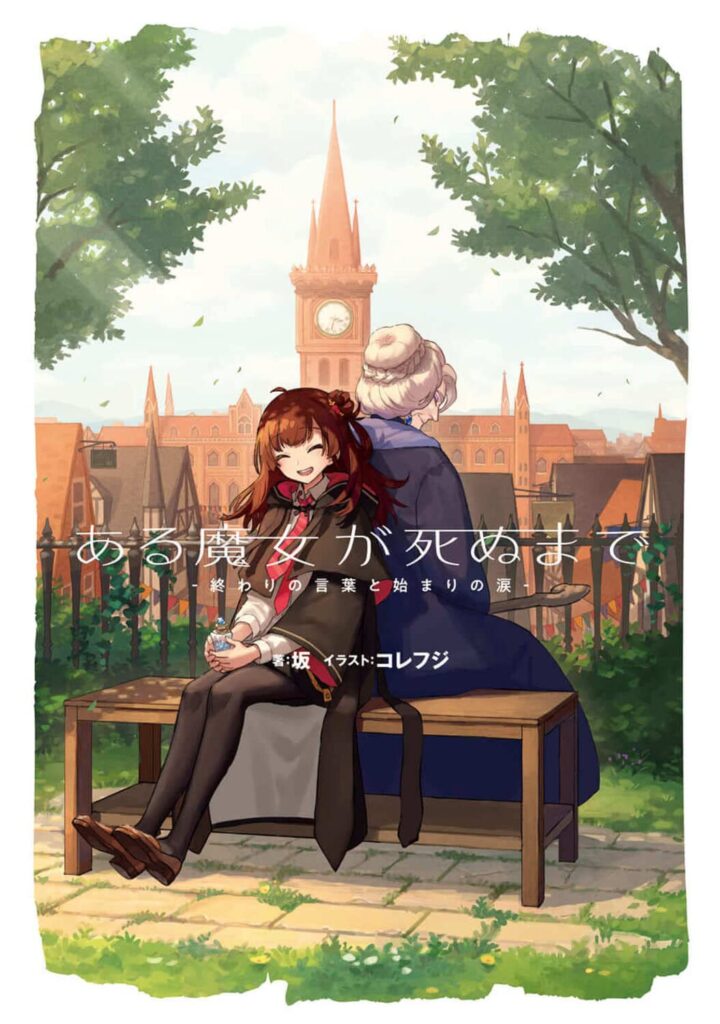


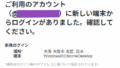
コメント